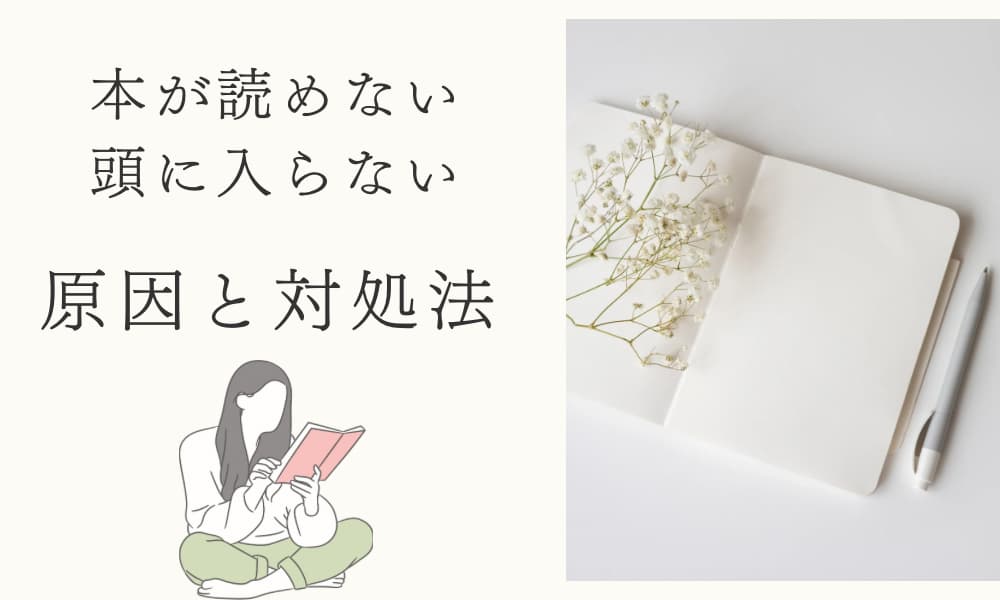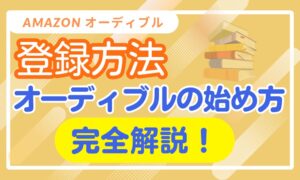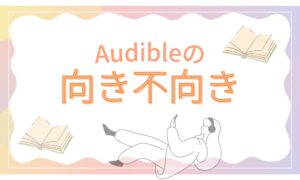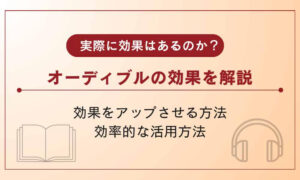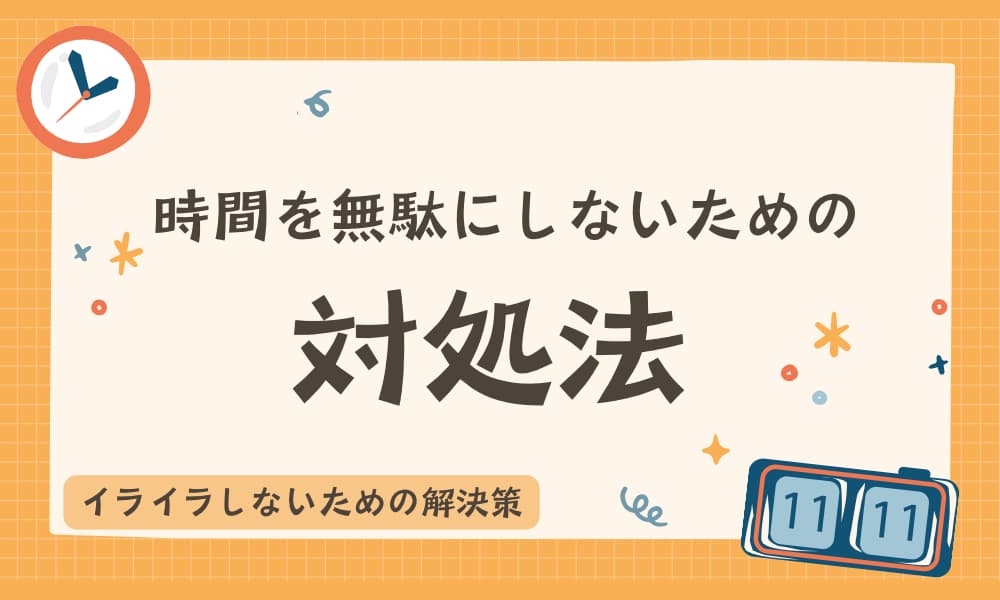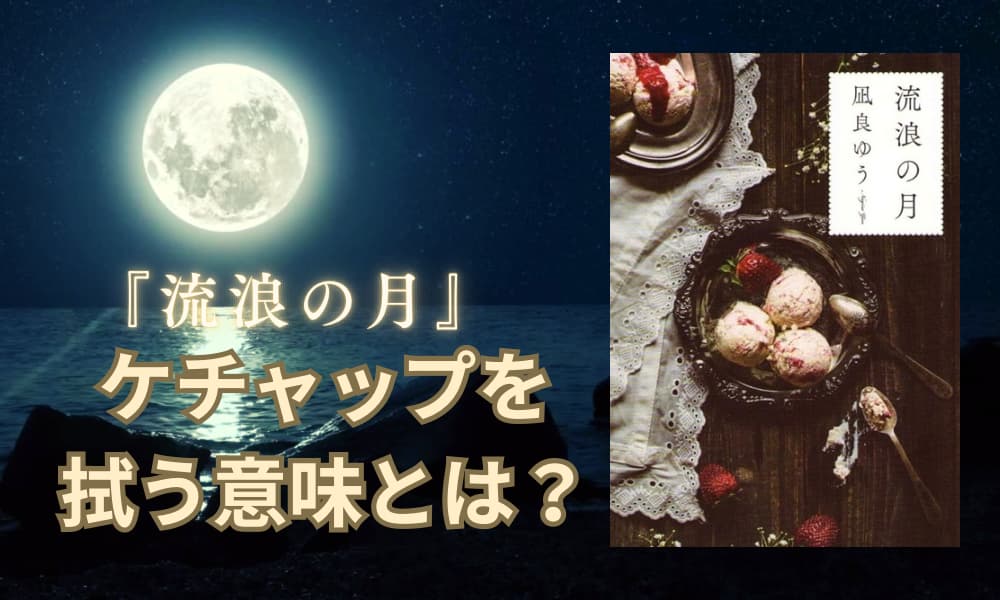「本を読んでも頭に入らない」「何度読み返しても内容が理解できない」――そんな悩みを抱えていませんか?
ストレスやスマホの使いすぎ、集中力の低下、あるいは発達障害や体調不良など、理由は人それぞれです。
この記事では、「本が読めない・頭に入らない」と感じる原因をわかりやすく解説しながら、無理なく内容を理解できる対処法を紹介していきます。
特におすすめしたいのが、オーディブル(Audible)を使った耳からのインプット。読めなくても、聴くことで知識がスッと入ってくる──そんな体験をぜひ試してみてください。

ユク
僕はオーディブルを使うことで、人生の時間の使い方が大きく変わりました。
公式サイト:https://www.audible.co.jp/
本が読めない、頭に入らない原因
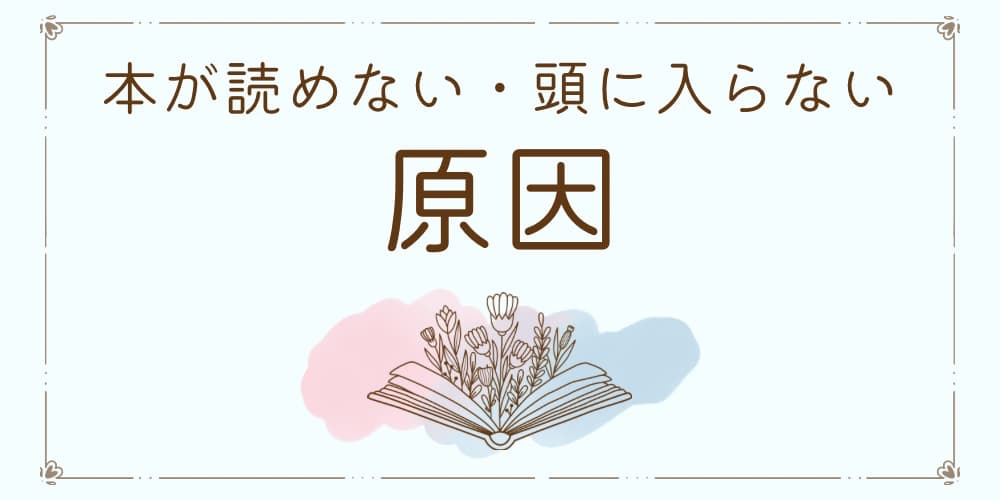
「読んでいるのに内容が頭に入ってこない」「何度読み返しても理解できない」――そんな経験はありませんか?
実は、ただの集中力不足ではなく、いくつかの要因が重なって「本が読めない」「頭に入らない」状態が起きていることが多いです。
ここでは、その代表的な原因を紹介します。
自分に当てはまりそうな項目があるか、確認しながら読み進めてみてください。
原因を知ることで、対策がぐっと立てやすくなりますよ。
- 文章が頭に入ってこないのはストレスのせいかも?
- スマホの使いすぎで集中力が続かない
- 発達障害やADHDの影響も考えられる
- 病気や体調不良による症状
- 勉強しても読んでも頭に入らない理由
文章が頭に入ってこないのはストレスのせいかも?
日々の生活や仕事でストレスが溜まっていると、集中力や記憶力が著しく低下します。
その結果、”文章を読んでいても頭に入ってこない”、”内容がスッと理解できない”といった状態に陥りがちです。
「なんだか最近、本を読んでもまったく集中できない」と感じているなら、ストレスが大きな原因になっている可能性があります。
まずは休息を取ったり、深呼吸や軽い運動などで心をリセットすることから始めてみましょう。ストレスが軽減されるだけでも、読書への集中力はぐっと高まりますよ。
スマホの使いすぎで集中力が続かない
つい手が伸びてしまうスマホ。便利な反面、知らず知らずのうちに集中力を奪う原因になっています。
SNSの通知や短い動画の連続視聴に慣れてしまうと、脳は「すぐに切り替わる情報」に慣れてしまい、長い文章や本を読み続ける力が弱まってしまうんです。
対策としては、読書の時間だけでもスマホを手の届かない場所に置いたり、通知をオフにする「集中モード」を活用するのがおすすめです。

ユク
僕は読書をするときは、スマホをそばに置かないようにしています。
スマホから少し離れるだけで、読書への没入感が驚くほど戻ってくることがあります。
発達障害やADHDの影響も考えられる
「本が読めない」「内容が頭に入らない」と感じる原因のひとつに、発達障害やADHDの特性が関係していることがあります。
特にADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある人は、注意がそれやすく、長い文章に集中し続けるのが難しいと感じやすい傾向があります。
「読もうとしても全然進まない」「何度読んでも理解できない」といった状態が長く続いている場合、自分を責めるのではなく、特性による影響かもしれないと視点を変えてみることも大切です。
読みづらさを感じる方には、音声で情報を得られるオーディブルのようなサービスが大きな助けになります。読むことにこだわらず、自分に合った方法で知識を取り入れる選択肢を持ちましょう。
病気や体調不良による症状
「本の内容が頭に入らない」「文字を読んでも全然集中できない」――そんな状態が続いているときは、体の不調や病気が関係している可能性もあります。
うつ病や自律神経の乱れ、慢性的な睡眠不足などがあると、脳の働きが低下し、注意力や記憶力が著しく落ちることも。
その結果、「文字が頭に入らない」「何度読んでも内容を覚えられない」といった症状が現れます。
一時的な疲労なら休息で回復しますが、体調を整えても読書に集中できない状態が続く場合は、一度医療機関で相談することも視野に入れてみましょう。

ユク
無理は禁物です。
勉強しても読んでも頭に入らない理由
「一生懸命勉強しているのに、全然覚えられない」「読んでも頭に残らない」――そんな悩みを抱える人は少なくありません。
その原因は、やり方の問題だけでなく、脳の状態や環境の影響が大きい場合があります。
集中力が散漫な状態で文字を追っても、記憶には定着しにくいもの。スマホの通知や、気が散るような音・視覚的な刺激がある環境では、なおさらです。
ただ読んでいるだけでは情報は入りにくく、インプットの方法に工夫が必要になります。
たとえば音声で聴くことで、リズムや抑揚によって内容が記憶に残りやすくなることがあります。読書が苦痛に感じるときは、聴く学習法への切り替えを検討してみてください。
本が読めない、頭に入らない時の対処法
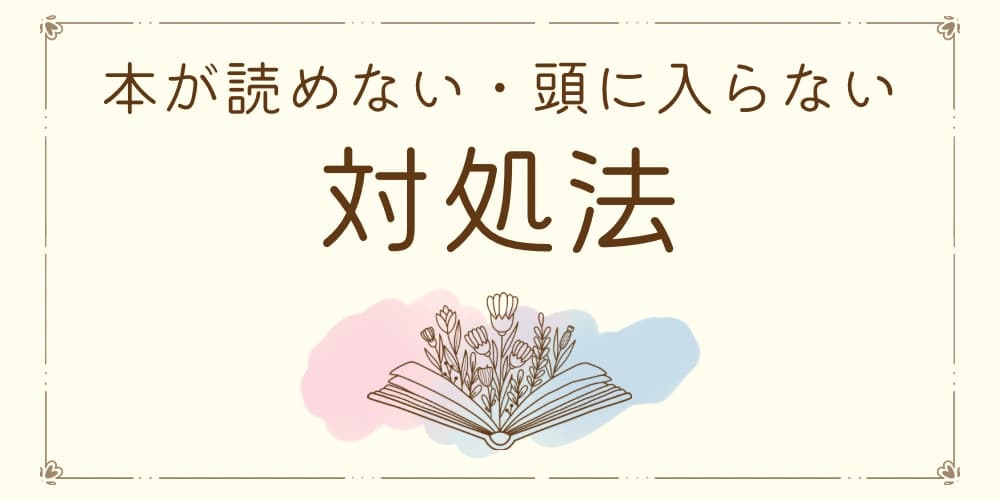
「読もうとしても集中できない」「何度読んでも内容が頭に入らない」――そんなとき、無理に頑張り続けるのは逆効果です。
大切なのは、自分の状態に合った方法に切り替えること。
ここでは、読書に集中できない原因に合わせて、実践しやすい対処法を紹介します。
まずは一番手軽で効果的な「オーディブルの活用」からご紹介し、そのほかの具体的な工夫もあわせて解説していきます。
自分にぴったり合う方法を見つけて、もう一度、読書や学びを楽しめる状態に戻していきましょう。
- 最初に試したい!オーディブルで「聴く読書」をはじめよう
- ストレスを感じたらまずはリラックスを
- ADHDや発達障害の傾向がある人にもオススメの方法
- スマホの通知を切って「集中モード」を作る
- 病気や不調がある場合は無理をしない
- 勉強に使うなら“聴いて復習”が効果的
最初に試したい!オーディブルで「聴く読書」をはじめよう
本を読むのがつらい、集中できない…。そんなときにこそ試してほしいのが、オーディブル(Audible)を使った「聴く読書」です。
オーディブルは、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービス。目を使わずに耳で内容をインプットできるため、疲れているときや集中力が落ちているときでも、無理なく学びを続けられます。
| 聴き放題本数 | 20万本 |
| 月額料金 | 1,500円(税込) |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード ※現金や電子決済は不可 |
| お試し期間 | 初めての入会で、30日間無料 (無料期間内に解約すれば、月額料金はかからない) |
通勤中や家事の合間、寝る前のリラックスタイムなど、ちょっとしたスキマ時間に“ながら読書”ができるのも大きなメリット。
文章が頭に入ってこないと感じていた人でも、「聴く」ことで不思議なくらいスッと理解できることがあります。
特に、ADHDや発達障害の傾向がある人にとって、音声でのインプットはストレスなく情報を受け取れる有効な手段になります。
読むのがつらいなら、読むのをやめてもいい。「聴く読書」で、自分に合った学び方を見つけてみましょう。
ストレスを感じたらまずはリラックスを
ストレスがたまっていると、どんなに頑張っても集中できず、内容がまったく頭に入らないことがあります。
そんなときは、まず「読もう」とする前に、心と体をリラックスさせることが大切です。
- 深呼吸をする
- 軽くストレッチをする
- 音楽を聴く
- 温かい飲み物を飲む
どんな方法でも構いません。自分なりの“ほっとできる時間”を意識的に取りましょう。
心が落ち着けば、脳の処理能力も回復しやすくなり、読書への集中力も自然と戻ってきます。
ADHDや発達障害の傾向がある人にもオススメの方法
ADHDの方は、気が散りやすく、長時間じっとして本を読むことが苦手な傾向があります。
また、発達障害の一部には「文章が頭に入らない」「読んでも理解しにくい」といった情報処理の難しさを抱えるケースも。
音声で情報を受け取ることで、活字へのストレスを減らし、より自然に内容を理解できるようになります。
読むことがつらいのなら、「聴く」という方法に切り替えてみましょう。
スマホの通知を切って「集中モード」を作る
本を読もうとしても、スマホの通知が鳴るたびに気が散ってしまう――そんな経験、ありませんか?
LINE、SNS、ニュースの通知など、ひとつひとつは小さくても、積み重なることで集中力を奪っていきます。
「文章が頭に入ってこない」「何を読んだかすぐ忘れてしまう」という状態の背景には、スマホによる断続的な注意の分断が潜んでいることも。
読書中はスマホを別の部屋に置く、通知が届かない設定にするなど、自分だけの静かな環境を意識的に作ることがポイント。
集中できる環境づくりは、読書の質を大きく左右します。
病気や不調がある場合は無理をしない
体調がすぐれないときや、精神的に落ち込んでいるときは、どれだけ本を開いても内容が頭に入らないことがあります。
それは怠けているのではなく、心や体が「休んでほしい」とサインを出している状態です。
うつ病や自律神経の乱れなど、目に見えにくい不調が原因で集中力や記憶力が落ちていることも少なくありません。

ユク
「読めない自分」を責めるのではなく、まずは無理をしない選択をしてあげてください。
頑張ることよりも、休むこと。
それが、また本を楽しめるようになるための大切なステップです。
勉強に使うなら“聴いて復習”が効果的
勉強しても内容が頭に残らない。何度読んでも覚えられない――そんなときは、「聴いて復習する」方法を取り入れてみましょう。
読むだけのインプットは、集中力や記憶力に左右されやすく、疲れているときは特に効率が落ちてしまいます。
例えば、通勤中や寝る前などのスキマ時間に復習音声を聴くことで、自然と知識が繰り返し脳に刷り込まれるのが大きなメリット。
特に「読んでも頭に入らない」「覚えられない」と感じている人ほど、視覚と聴覚を組み合わせた学習法は効果を発揮します。
読むだけにこだわらず、“聴く勉強”という選択肢を持つことで、学びがもっと楽になり、続けやすくなります。
公式サイト:https://www.audible.co.jp/
本が読めない、頭に入らない原因と対処法:まとめ
本が読めない、頭に入らない――その背景には、ストレスやスマホの影響、発達特性、体調不良など、さまざまな要因が関係しています。
まずは「読めない自分を責めないこと」が何より大切です。
無理に文字を追い続けるのではなく、自分に合った方法に切り替えることで、読書や学びはもっとラクになります。
中でも「聴く読書」は、多くの人にとって効果的でやさしい選択肢。オーディブルのような音声サービスを取り入れることで、読むのが苦手でも自然に内容が頭に入ってくる感覚を味わえます。
原因を知り、自分に合った対処法を見つけること。
それが、「また本を楽しめる自分」への一歩になります。